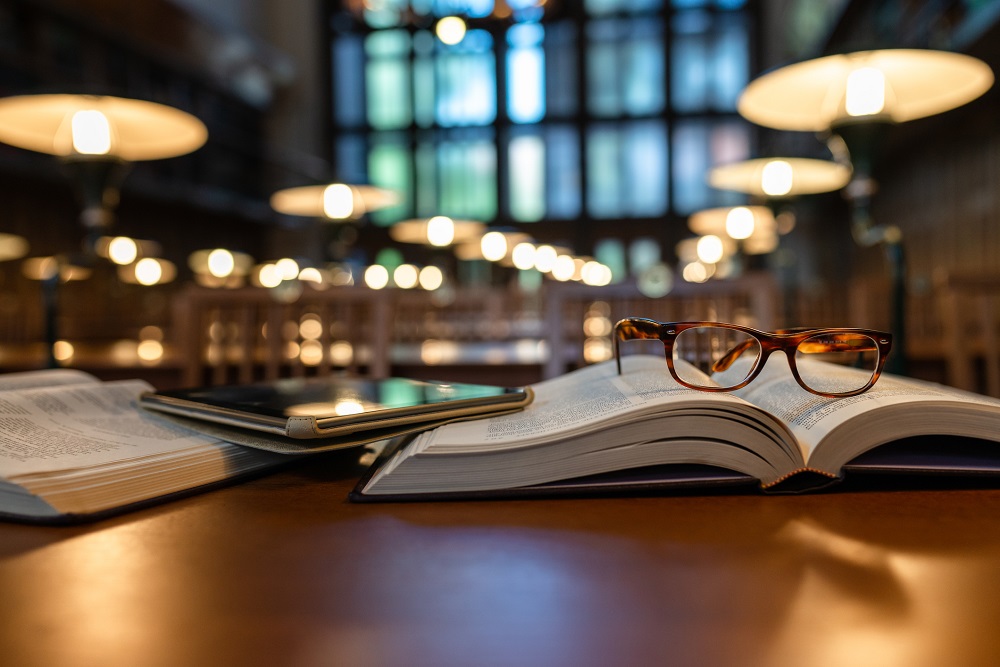
Generative AIの教育分野での活用について、学習効率化への期待と不適切な使い方への懸念が交錯している。
Generative AIはテキストや画像、音楽などを生成する人工知能(AI)の総称で、OpenAIが公開したChatGPTやMicrosoftのBing Chatが注目を集めている。
2023年7月4日、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を公表した。使いこなすための力を意識的に育てていくことは重要であるとしつつ、活用にあたっては児童生徒の発達段階を十分に考慮する必要があるとして、教育者に一定の配慮を求める内容である。公教育では、Generative AIの活用に対し慎重な姿勢が保たれている。
一方、23年春頃から、Generative AIを組み込んだ教育向けサービスやアプリケーションが、民間企業から次々とリリースされている。英会話アプリでの導入とマネタイズが先行しているように見えるが、他にもユニークな事例が多数ある。
例えば、atama plusがリリースした「物語文で単語学習機能(β版)」は、タブレット学習で生徒の英単語の習熟度を把握し、定着が不十分な英単語が登場する長文をGenerative AIが自動生成するというものである。苦手な単語に文章中で触れる機会を増やすことで、記憶の定着を早めよう。
10年代に普及したアダプティブ・ラーニングは、問題データベースから学習者に最適な問題を“選定”するという点で画期的であった。Generative AIが登場し、最適な問題を“生成”できるようになったことで、アダプティブ・ラーニングは次のステージへ移行するだろう。
Trippyは、人気ドラマの教師をモデルにしたキャラクター(AI)が学習者からの質問に、LINE上で答えるサービスをリリースしている。学習者は質問を躊躇する必要がなく、24時間いつでも何度でも回答してもらえる。Generative AIをチューニングすることで親近感のあるキャラクターを作り込めば、学習者のモチベーションを高められる可能性がある。キャラクターとの対話を通じて、進路を考えたり、学習計画を練ったりすることもできるだろう。
Generative AIの普及は、学習を“与えられるもの”から“自発的にやりたくなるもの”に変化させ得る。
(野村證券フロンティア・リサーチ部 小川 裕一郎)
※野村週報 2023年7月24日号「新産業の潮流」より
※掲載している画像はイメージです。

 検索する
検索する






