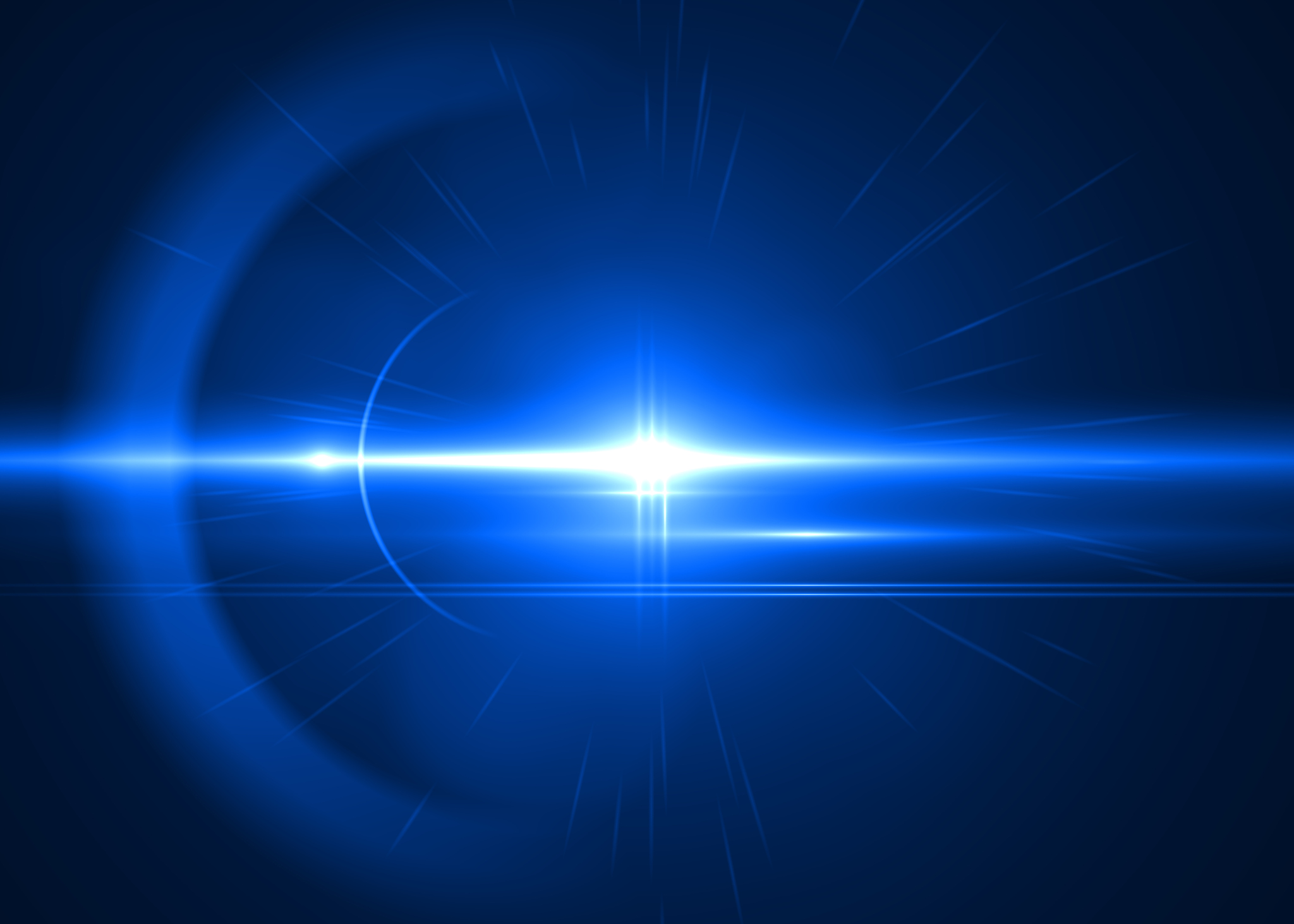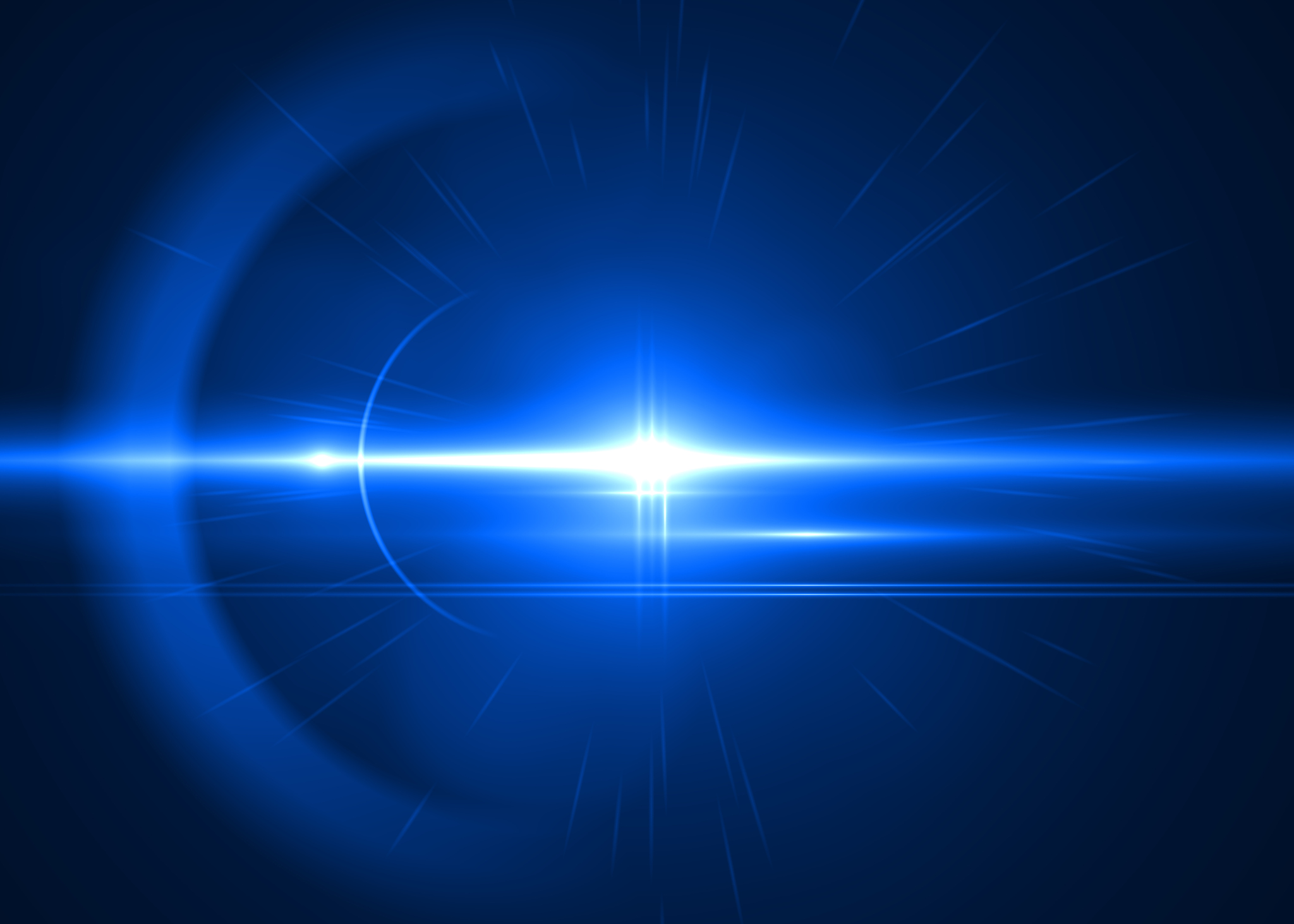
二酸化炭素を排出しない新しいエネルギー源として核融合発電が注目されている。
核融合発電は、重水素と三重水素を1億℃以上の高温でプラズマ状態にして核融合反応を起こし、熱エネルギーを生み出して電気エネルギーに変換する仕組みである。原料資源の偏在や高レベル放射性廃棄物の最終処分など、原子力発電が抱える課題を解決する技術と期待される。
核融合発電には複数の方式があり、それぞれ技術開発が進められている。2022年12月には、米ローレンス・リバモア研究所の国立点火施設(NIF)が世界で初めて、投入したレーザーエネルギーより多くのエネルギーを産生し、(科学的な)エネルギー純増の達成として話題になった。
NIF で開発しているのはレーザー核融合である。レーザー核融合では、重水素と三重水素を原料とした燃料ペレットを、強力なパルスレーザーで周囲から高密度で圧縮・加熱し、核融合を発生させる。
ただし、今回のNIF のエネルギー純増達成では、レーザーを生み出すために、産生したエネルギーの100倍超の電力を消費しており、実質的なエネルギー純増は未達成である。また、レーザー核融合発電には、核融合を1秒間に10回(10Hz)繰り返す必要があるが、NIF のレーザー設備は8時間に1回しか照射することができない。

レーザー核融合発電の実現に必須の、高効率かつ高出力で高頻度に照射を繰り返せるレーザーの開発では、浜松ホトニクスが23年1月に、高効率な半導体レーザーを用いて世界でも最高水準の出力100ジュール・10Hzを達成した。同社は、今後3~5年で出力を現在の10倍に引き上げることを目指している。
高出力レーザー装置で発生した複数のレーザーを結合すれば、レーザー核融合に必要なエネルギーを得ることができる。そのために必要な精緻なレーザー制御技術を開発する企業例としては、大阪大学発スタートアップであるEX-Fusionが挙げられる。
レーザー以外にも、高品質な燃料ペレットや、ペレットを反応炉に投入するインジェクターなど、レーザー核融合の実用化には多くの技術的課題が残っている。日本はレーザー核融合の研究水準が高く、関連する技術開発も進んでおり、今後の動向が期待される。
(フロンティア・リサーチ部 横山 恭一郎)
※野村週報 2023年2月6日号「新産業の潮流」より

 検索する
検索する