★野村アプリ向け

411件
-
 08/02 16:00
08/02 16:00【注目トピック】日米欧、主要中銀の政策金利見通し 3者3様の金融政策スタンス
※画像はイメージです。 ECBは8会合ぶりに利下げを見送り ECBは2025年7月24日に定例理事会を開催し、政策金利を2.00%(中銀預金金利)で据え置きました。政策金利の据え置きは8会合ぶりとなります。ECBは24年6月会合での利下げを契機に利下げ局面入りし、同年9月以降7会合連続での利下げを含み、累計2.00%ポイントの利下げを実施しました。理事会後の記者会見でラガルド総裁は、「我々は様子見できる好ましい位置にある」と発言し、当面政策金利を据え置く可能性を示唆しました。 野村證券は従来、ECBが25年9月と12月に追加利下げを実施し、中銀預金金利の着地点は1.50%になると予想してきましたが、7月会合の結果を受けて見通しを修正し、前回6月会合での利下げで今回の利下げ局面は終了したと判断しています。 ユーロ圏政策金利と独10年国債利回りの推移 (注)データは日次で、直近値は2025年7月30日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 FRBは5会合連続で据え置き FRBは25年7月29-30日にFOMCを開催し、予想通り政策金利であるFF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標を4.25-4.50%に据え置きました。政策金利の据え置きは5会合連続です。今回はボウマン副議長とウォラー理事が0.25%ポイントの利下げを主張し、決定に反対しました。ただし、事前の予想通りであり、市場に対する明確な影響は確認できませんでした。 会合後の記者会見でパウエル議長は経済活動の伸び鈍化について、「主に個人消費の減速を反映している」と説明しました。また、「大半の政策当局者は利下げを急ぐべきではないと主張している」としたうえで、9月会合での利下げを示唆することを避けました。市場ではパウエル議長の発言がタカ派的(利下げに消極的)と捉えられ、1回当たりの利下げ幅を0.25%ポイントとした場合、25年中の利下げ期待がFOMC前の1.8回から1.5回へと低下しました。 米国の政策金利見通し (注)データは日次で、直近値は2025年7月30日。政策金利はFF(フェデラル・ファンド)金利誘導目標の中央値。FF金先はFF金利先物。(出所)FRB、ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 日銀はインフレ見通しのリスクバランスを上方修正 日本銀行は25年7月30-31日に金融政策決定会合を開催し、事前予想通り全会一致で政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.5%程度で据え置くことを決定しました。日銀による政策金利据え置きは4会合連続となります。 同時に公表した「展望レポート」では、食料品価格の上昇を主因に25年度の消費者物価(除く生鮮食品)の見通しを上方修正した一方、実質GDPや26年度以降のインフレ見通しについては微修正にとどめました。日銀は景気の先行きについて、海外景気の減速、企業収益の下押しなどを背景に減速を見込むものの、その後は「海外経済が緩やかな成長経路に復していくもとで、成長率を高めていく」との見通しを示しました。その上で、基調的なインフレ率に関しては、「見通し期間後半には「物価安定の目標」と概ね整合的な水準で推移すると考えられる」との見方を維持しています。 展望レポートの経済見通しを踏まえると、経済・物価が見通しに沿って推移すれば、利上げで緩和度合いを調整していく方針に変更はないと考えられます。ただし、経済に関するリスクバランスは25年度、26年度ともに「下振れリスクの方が大きい」との表現を据え置いた一方、物価見通しに関しては前回の「下振れリスクの方が大きい」から「概ね上下にバランスしている」へと変更しました。このため、市場では早期利上げ観測やターミナルレート(政策金利の最終着地点)見通しの上方修正期待につながることが予想されます。 展望レポートにおける「政策委員の大勢見通し」(2025年7月) (注)値は、前年度比%で、<>内は政策委員見通しの中央値。各政策委員は、既に決定した政策を前提として、また先行きの政策運営については市場の織り込みを参考にして、上記の見通しを作成している。「大勢見通し」は、各政策委員が最も蓋然性の高いと考える見通しの数値について、最大値と最小値を1個ずつ除いて、幅で示したものであり、その幅は、予測誤差などを踏まえた見通しの上限・下限を意味しない。(出所)日本銀行資料より野村證券投資情報部作成 主要中銀の政策金利見通し 野村證券では、ECBの利下げは打ち止めとなり、今後は据え置きを予想しています。 FRBに関しては、インフレのピークアウトが視野に入ると予想される25年12月から3会合連続で0.25%ポイントずつの利下げを予想しています。ターミナルレートは3.50-3.75%の見通しです。 日銀に関しては26年1月に0.75%へ利上げした後、据え置きに転じると、3者3様の展開を予想しています。 日米欧の政策金利の推移 (注)政策金利は日本:無担保コール翌日物金利、2016年2月~24年2月は政策金利残高適用金利。米国:FF(フェデラル・ファンド)金利誘導目標の上限、ユーロ圏:中銀預金金利。データは月次で直近値は2025年6月。野村予想は、2025年7月末~2026年12月末で、2025年7月25日時点。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 野村證券投資情報部 シニア・ストラテジスト尾畑 秀一 1997年に野村総合研究所入社、2004年に野村證券転籍。入社後、一貫してエコノミストとして日本、米国、欧州のマクロ経済や国際資本フローの調査・分析に従事、6年間にわたり為替市場分析にも携わった。これらの経験を活かし、国内外の景気動向や政策分析、国際資本フローを踏まえ、グローバルな投資戦略に関する情報を発信している。 ご投資にあたっての注意点
-
 08/02 12:00
08/02 12:00【#設備投資】AI抽出15銘柄/きんでん、関電工、GSユアサなど
日本企業の設備投資、2年連続で過去最高を更新 日本経済新聞社がまとめた2025年度の設備投資動向調査で、全産業の計画額が前年度実績比12.4%増の34兆2663億円となり、2年連続で過去最高を更新しました。日本企業が成長分野への投資を強化することで、産業構造の転換や国際競争力の向上も期待されます。AI「xenoBrain」は、「企業設備投資増加」が他のシナリオにも波及する可能性を考慮し、影響が及ぶ可能性のある15銘柄を選出しました。 ※ xenoBrain 業績シナリオの読み方 (注1)本分析結果は、株式会社xenodata lab.が開発・運営する経済予測専門のクラウドサービス『xenoBrain』を通じて情報を抽出したものです。『xenoBrain』は業界専門誌や有力な経済紙、公開されている統計データ、有価証券報告書等の開示資料、及び、xenodata lab.のアナリストリサーチをデータソースとして、独自のアルゴリズムを通じて自動で出力された財務データに関する予測結果であり、株価へのインプリケーションや投資判断、推奨を含むものではございません。(注2)『xenoBrain』とは、ニュース、統計データ、信用調査報告書、開示資料等、様々な経済データを独自のAI(自然言語処理、ディープラーニング等)により解析し、企業の業績、業界の動向、株式相場やコモディティ相場など、様々な経済予測を提供する、企業向け分析プラットフォームです。(注3)母集団はTOPIX500採用銘柄。xenoBrainのデータは2025年7月28日時点。(注4)画像はイメージ。(出所)xenoBrainより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
-
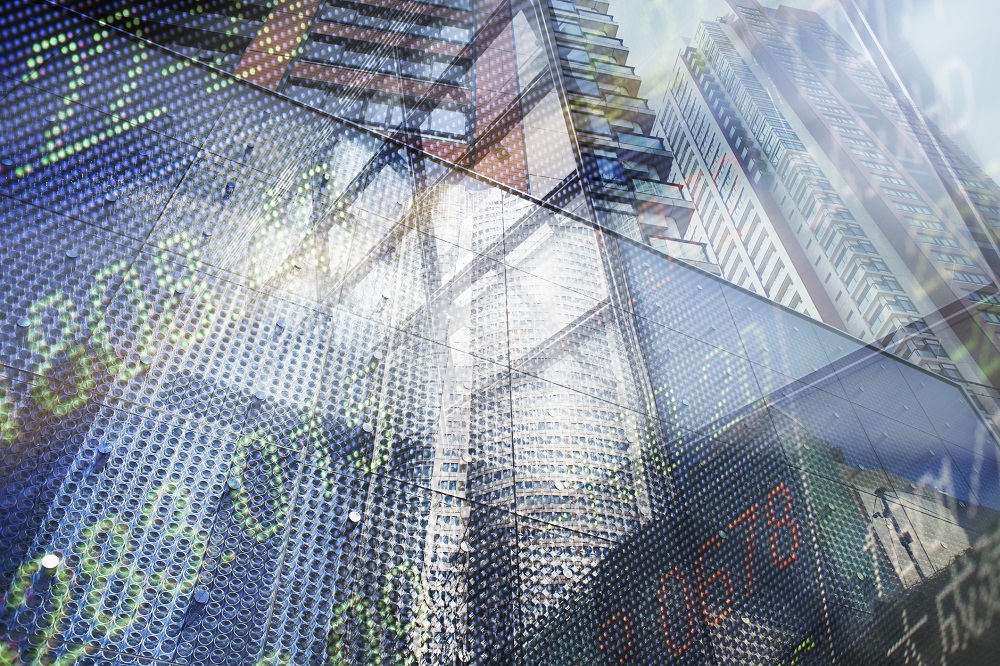 08/02 09:00
08/02 09:00【オピニオン】自社株買いを続ける企業の探し方
※画像はイメージです。 ラッセル野村Large Cap(除く金融)の2025年度経常利益は2025年7月30日時点で前期比-7.7%と減益予想となっています。背景に、不透明な米トランプ政権による関税政策があることは間違いありません。我が国を含む一部の国・地域とは関税交渉が妥結に至っていますが、関税の適用による経済・業績への実際の影響は未知数です。 このため、2025年度がスタートした当初は、一部に「2025年度の自社株買いは期待薄ではないか」との見方も存在しました。しかし、2025年6月末時点で自社株買い設定額は9.3兆円と、同時期としては過去最高となる好発進となっています。 不透明な環境にもかかわらず、なぜ企業は積極的に自社株買いの枠を設定したのでしょうか?おそらく、①長期金利の上昇に伴いWACC(加重平均資本コスト、4.83%注)も上昇し、一方②減益予想のためROIC(投下資本利益率、5.09%注)が低下し両者がほぼ拮抗する状態に陥る可能性が高いが、③益利回り(PERの逆数)はWACCを顕著に上回った状態にあり、④自社株買いが望ましい財務的な行動として認識されている、ものと考えられます。 なお、この流れは全産業レベルで言えることですが、業種・企業により状況は異なります。 業種別 WACC(加重平均資本コスト)と益利回り (注)RNLを構成する18業種(金融を除く)。 RNLはラッセル野村Large Capの略。▲はWACCで2025年6月16日時点の2025年度予想。+は2025年度基準益利回り、+は2026年度基準益利回りで、いずれも2025年7月30日時点。(出所)野村證券市場戦略リサーチ部などより野村證券投資情報部作成 益利回りがWACCを顕著に上回り、自社株買いが望ましいと考えられる業種は、商社、通信、建設など、内需・非製造業に多く見られます。ただし、製造業でも関税の影響が一巡すると考えられる2026年度基準の益利回りでは自社株買いが望ましいと考えられる業種が数多く存在しています。 なお蛇足ながら、株式市場で評価の高い業種の1つであるソフトウエアでは、これまでのところ自社株買いを発表している企業は13%(全産業平均19%)に留まっており、企業側がWACCと益利回りを天秤にかけている様子が垣間見えます。 今局面では政策保有株を減らし、自社株買いに充当するケースも多数みられます。これは、過剰な自己資本の積み上がりを防ぎ、低リターンな資産を減らし、資産規模の膨張も防げることから望ましい財務行動であることは間違いありません。ただし、政策保有株の売却を永続的に行うことは不可能です。 継続的に自社株買いを行うであろう業種・企業は、資産・資本効率向上の意思があることに加えて、今回紹介したような、WACC/ROIC/益利回りが望ましい状況にあること、が条件となるでしょう。 (注)数字はいずれも2025年6月16日時点の2025年度予想。 ROIC(投下資本利益率)は、NOPAT/IC。ただし、NOPATは、営業利益×(1-税率)。ICは、自己資本+有利子負債。WACC(加重平均資本コスト)は、D/(D+E)×Rf×(1-t)+E/(D+E)×(Rf+Rp)。ただし、Dは有利子負債、Eは自己資本、tは税率、Rfは10年債パーイールドの期中平均、Rpはイールドスプレッド。 ご投資にあたっての注意点
-
 08/02 07:00
08/02 07:00【来週の予定】金融政策の見極めには丁寧な経済指標の確認が必要
来週の注目点:日米中の企業景況感、米中の貿易統計 前週は各国で金融政策会合が開催される中銀ウィークでした。7月FOMCでは、事前予想通り政策金利が据え置かれました。関税は今後数ヶ月、インフレ圧力となる可能性が高く、労働市場に明確な悪化の兆候がない限り、しばらく政策当局は利下げに慎重なスタンスを続けると野村證券では予想します。また、パウエルFRB議長が政策の方向性はデータ次第との認識を改めて示す中、今後も丁寧に経済指標を確認していく必要がありそうです。米国では、5日(火)に6月貿易統計、7月ISMサービス業景気指数が発表されます。関税発動前の在庫を積み増す動きが落ち着き、財の輸入が落ち込んだと野村證券では予想します。 他方、前週の日銀金融政策決定会合では、政策金利を据え置いた上で、物価見通しを上方修正し、利上げ姿勢を継続しました。今後の日銀の金融政策を占う上では、5日(火)発表の6月日銀金融政策決定会合議事要旨、8日(金)発表の7月日銀金融政策決定会合における主な意見が参考になります。 日本の経済指標では、6日(水)に6月毎月勤労統計が発表されます。一般労働者の所定内給与(基本給等)や、夏季賞与の上昇率に注目です。また、8日(金)発表の7月景気ウォッチャー調査は、日米の関税交渉合意後の7月25日から31日に調査されたことから、合意が企業の景況感や生産計画に与えた影響に注目が集まります。 中国では、5日(火)に7月S&P Global中国・サービス業PMI、7日(木)に7月貿易統計が発表されます。米中の関税一時停止期限の8月を前に行われた輸出の前倒しが失速する可能性があります。また、7月から政府が実施している過度な価格競争を抑制する規制強化が生産を下押しした可能性があります。さらに、公務員等に対して5月から実施している豪華な宴会等を禁止する「倹約令」が消費を下押したと見られます。景気の下押し材料が増えつつあり、足元の企業景況感の悪化が懸念されます。 (野村證券投資情報部 坪川 一浩) (注1)イベントは全てを網羅しているわけではない。◆は政治・政策関連、□は経済指標、●はその他イベント(カッコ内は日本時間)。休場・短縮取引は主要な取引所のみ掲載。各種イベントおよび経済指標の市場予想(ブルームバーグ集計に基づく中央値)は2025年8月1日時点の情報に基づくものであり、今後変更される可能性もあるためご留意ください。(注2)画像はイメージです。(出所)各種資料・報道、ブルームバーグ等より野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
-
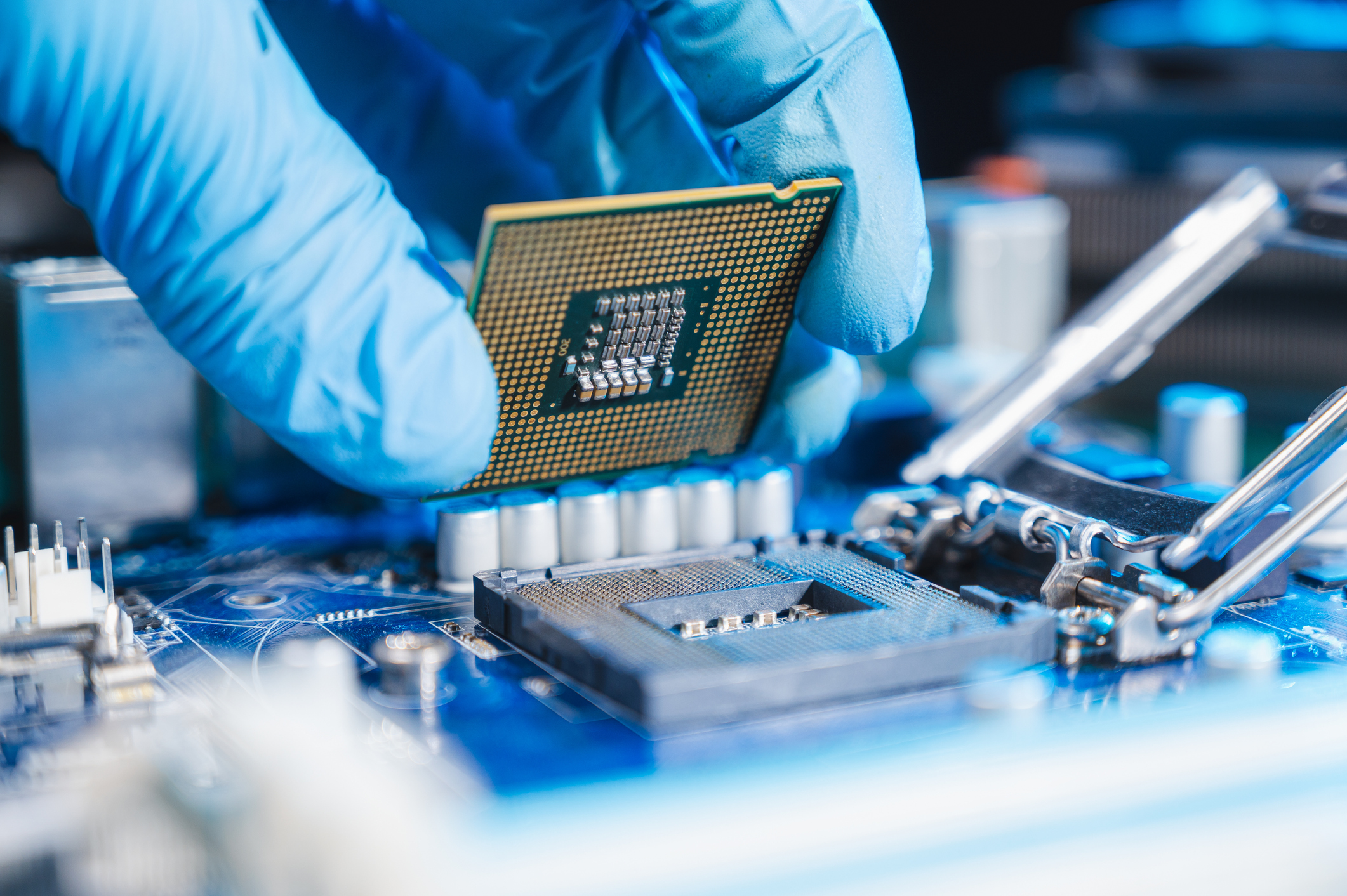 08/01 16:00
08/01 16:00【野村の夕解説】半導体関連株の急落で、日経平均株価は270円安(8/1)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 7月31日引け後、東京エレクトロンが2025年4-6月期決算発表で、顧客企業の投資減や投資計画の見直しなどを理由に半導体製造装置市場の見通しを下方修正しました。これを受けて、1日の日本株市場では同社を含む半導体関連株が大幅安となりました。日経平均株価は寄り付きから下落、一時前日比481円安の40,588円まで下げ幅を広げました。その後は1米ドル=150円90銭台まで円安が進んだことを支えに、下げ幅を徐々に縮小しました。米国では7月FOMCを受けて早期利下げ再開への期待が後退する一方、31日の日銀金融政策決定会合後、植田総裁は関税を巡る不確実性の高い状況が続くことから、利上げ再開を急がない姿勢を示しました。これらを受けて、日本時間31日引け後以降、急速に円安が進みました。日経平均株価は午後の取引開始直後に前日比70円安の40,999円まで回復したものの、円安進行の一服とともに引けにかけて再度下げ幅を広げ、終値は前日比270円安の40,799円となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 米国でFRBが重視する7月雇用統計が発表されます。前日までに発表された7月ADP全米雇用レポートや7月26日の週の週間新規失業保険申請件数では、米国労働市場の底堅さが示されましたが、同様の結果となるか注目されます。 (野村證券投資情報部 秋山 渉) ご投資にあたっての注意点
-
 08/01 12:00
08/01 12:00【今週のチャート分析】日経平均株価、高値警戒感から押しを入れる
※画像はイメージです。 ※2025年7月31日(木)引け後の情報に基づき作成しています。 25日移動平均線を下支えとして反発なるか注目 今週の日経平均株価は、週前半に高値警戒感から売りが優勢となりました。しかし7月31日には、円安の進行などを背景に5営業日ぶりに反発しました。 日足チャート(図1)では、日米関税交渉合意を受けて7月23日に年初来高値を更新し、翌24日には一時42,000円台を付けました。ただ、その後は一旦押しを入れる動きとなり、30日には一時40,556円まで下落しました。この先同水準を割り込みさらなる調整となった場合は、6月以降何度も下支えとなってきた25日線(7月31日:40,161円)が下支えになることが期待されます。 (注1)直近値は2025年7月31日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 一方で、6月以降、複数の上値抵抗線を次々に突破していることから、中長期的な上昇局面に入っている可能性が高いとみられます。今後も一時的な調整をこなしながら、高値を更新していく展開となると考えられます。次の上値メドとしては、7月24日の高値(ザラバベース:42,065円)や、6月30日高値から7月14日安値までの押し幅の倍返しにあたる42,416円、さらには昨年7月に付けた史上最高値(同:42,426円)が挙げられます。 日経平均 過去の主要上昇局面比較で上昇余地 日経平均株価は、今年4月に米国相互関税への懸念から大幅安となりましたが、その後は一転大幅上昇となっています。今回は2010年以降の主な4回の上昇局面と今年4月安値以降の上昇局面を比較し、先行きを検討します(図2)。 (注1)直近値は2025年7月31日時点。(注2)主要な上昇局面は全てを網羅している訳ではない。(注3)起点はそれぞれ以下の安値とした。①当時の野田首相による衆議院解散(12/11/16)前の安値、 ②英国の国民投票でEU離脱が多数を占めたブレクジット時の安値、 ③コロナショック時の安値、④2023年3月の東証要請前の安値、今回は2025年4月のトランプ相互関税発表後の安値。(注4)東証要請は、東証が上場企業に対して資本コストや株価を意識した経営を要請したことを示す。企業ガバナンス改革への期待感が株価を押し上げた。 (出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 まず今回は、過去4回のいずれの株価ピークにも達しておらず、今後も上昇余地があると考えられます。また、7月31日時点では、アベノミクス相場(図中:①)やコロナショック後の急回復局面(同:③)と類似した動きが見られ、これら局面と比較した場合、特に上昇期待が高まります。一方で、東証要請や生成AIへの期待で上昇した前回の中長期局面(同:④)と比べると、今回はやや過熱気味で、一時的に上値が抑えられる可能性もあります。 ただ、今回は既に下降トレンドラインの上抜けや52週移動平均線越えといったチャート上の強気サインが確認されており、これらを踏まえると、仮に一時的に押しが入る局面があっても中長期的には上昇が継続すると見込まれます。 (野村證券投資情報部 岩本 竜太郎) ご投資にあたっての注意点
-
 08/01 09:01
08/01 09:01【米国株決算速報】アップル(AAPL):iPhone・サービス好調・AI強化へ注力、株価は+2.29%(時間外取引)
決算概要:2025年4-6月期(2025.9期第3四半期) EPS実績は市場予想を上回った 米国時間7月31日引け後に、モバイル端末の製造販売とAI・クラウドサービス事業を行うアップル(AAPL US)が2025年4-6月期(2025.9期第3四半期)決算を発表しました。売上高は市場予想を5.0%上回り、EPSは市場予想を9.5%上回りました。 iPhone・サービス好調、AI強化へ注力 主力製品であるiPhoneの売上高が市場予想を上回り、それにより保証などのサービス売上高も堅調でした。会社は、顧客による製品のアップグレードが4-6月期として過去最高だったとコメントしました。また、会社の2025年7-9月期売上高見通しは市場予想を上回り、市場の一部にあった関税前の駆け込み購入の後に需要が減少する、との懸念が和らぎました。 会社は市場で遅れが指摘されているAI事業について、今年に入り7社を買収し、人員を再配分しているとコメントし、注力する姿勢を強調しました。 売上高とEPSの推移 株価は時間外取引で上昇 アップルの株価は、前日比0.71%安で引けた後、決算発表を受けて時間外取引では、終値比2.29%高の212.32ドルで推移しています(NY時間18:45)。市場予想を上回る好調な実績や見通しに反応していると考えられます。今後は、関税の影響に加え、9月に予定されている新製品の詳細や、年末商戦について注目する必要があると考えられます。 株価推移 (6ヶ月日足) (注1)EPS は米国会計基準の希薄化後一株当たり利益。2025年7-9月期売上高見通しの市場予想比は前年比7%成長で試算。(注2)株価推移:データは日次で、直近値は2025年7月31日時点。(注3)売上高とEPSの推移:赤色は実績で、直近値は2025年4-6月期(2025/6)。2025年7-9月期の売上高の白丸は会社見通し中間値。灰色はLSEG集計による市場予想平均。2025年7-9月期以降の予想は2025年7月30日時点。(出所)会社発表、LSEGより野村證券投資情報部作成 (文責:野村證券 投資情報部・竹綱 宏行) ご投資にあたっての注意点
-
 08/01 08:18
08/01 08:18【野村の朝解説】S&P3日続落、米ドル円は150円台後半へ(8/1)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 31日の米国市場でS&P500は、一時は取引時間中の最高値を更新したものの、結局3日続落して引けました。マイクロソフト、メタ・プラットフォームズなどの好決算も指数全体を押し上げるまでには至りませんでした。為替市場では米ドルがG10通貨に対して全面高となり、対円では200日移動平均線(149円59銭)を5ヶ月半ぶりに上抜けし、150円台後半で推移しています。決定会合後の植田総裁の発言が、市場では想定以上にハト派的(利上げに消極的)と受け止められたようです。 相場の注目点 7月の金融政策会合では日銀、FRB、ECBともに事前の予想通り政策金利の据え置きを決定しました。ただし、今後の政策スタンスは3者3様です。ECBの利下げ見送りは8会合ぶりであり、ラガルドECB総裁は追加利下げに慎重な姿勢を示しました。FRBの金利据え置きは5会合連続です。パウエル議長は利下げを急がない意向を示唆しました。日銀も4会合連続で政策金利を据え置きました。経済・物価が見通しに沿って推移すれば政策金利を引き上げる方針に変更はない様子であり、植田総裁の発言にも大きな変化は確認できませんでした。米国と日本、EUの間で関税協定が合意に達したことから、今後は金融政策スタンスの違いによる影響が、為替相場を筆頭に、金融市場動向にも波及することが予想されます。 本日のイベント 米国では新たな関税が発動される予定です。ただし、詳細が明らかになっていないものも多く、現場では混乱が予想されています。また、7月雇用統計、 7月ISM製造業景気指数と重要指標が発表されます。失業率が予想外に上昇すれば、市場の早期利下げ観測を喚起する可能性があります。 (野村證券 投資情報部 尾畑 秀一) (注)データは日本時間2025年8月1日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ご投資にあたっての注意点
-
 07/31 16:56
07/31 16:56【野村の夕解説】日経平均415円高 米企業の好決算と円安が追い風(7/31)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 30日の米国市場で発表された大手テクノロジー企業の2025年4-6月期決算で、見通しを含めた好調な業績が示されるとともに、市場ではAI・データセンター向け投資拡大継続の見方が強まりました。また、米国で30日まで開かれていたFOMCの結果を受けて、FRBによる9月利下げ再開への期待が後退し、為替市場で一時1米ドル=149円台半ばまで、急速な円安米ドル高が進みました。これらを背景に、31日の日経平均株価は寄り付きから上昇、ソフトバンクグループやフジクラなどAI・データセンター関連銘柄がけん引役となったほか、朝方は下落していた値がさの半導体関連株が上昇に転じ、日経平均株価を押し上げました。12時頃、日銀が政策金利の据え置きを発表しました。併せて公表された展望レポートで、経済に関するリスクバランスは2025年度、2026年度ともに「下振れリスクの方が大きい」との表現を据え置きました。これを受けて10年国債利回りは前日比で低下しました。金利低下を追い風に日経平均株価は午後に入って更に上げ幅を広げ、終値は前日比415円高の41,069円となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 米国でFRBが重視する6月のコアPCEデフレーター(食品・エネルギーを除く個人消費支出物価指数)が発表されます。関税の影響を確認するうえで注目が集まります。 (野村證券投資情報部 秋山 渉) ご投資にあたっての注意点

 検索する
検索する

