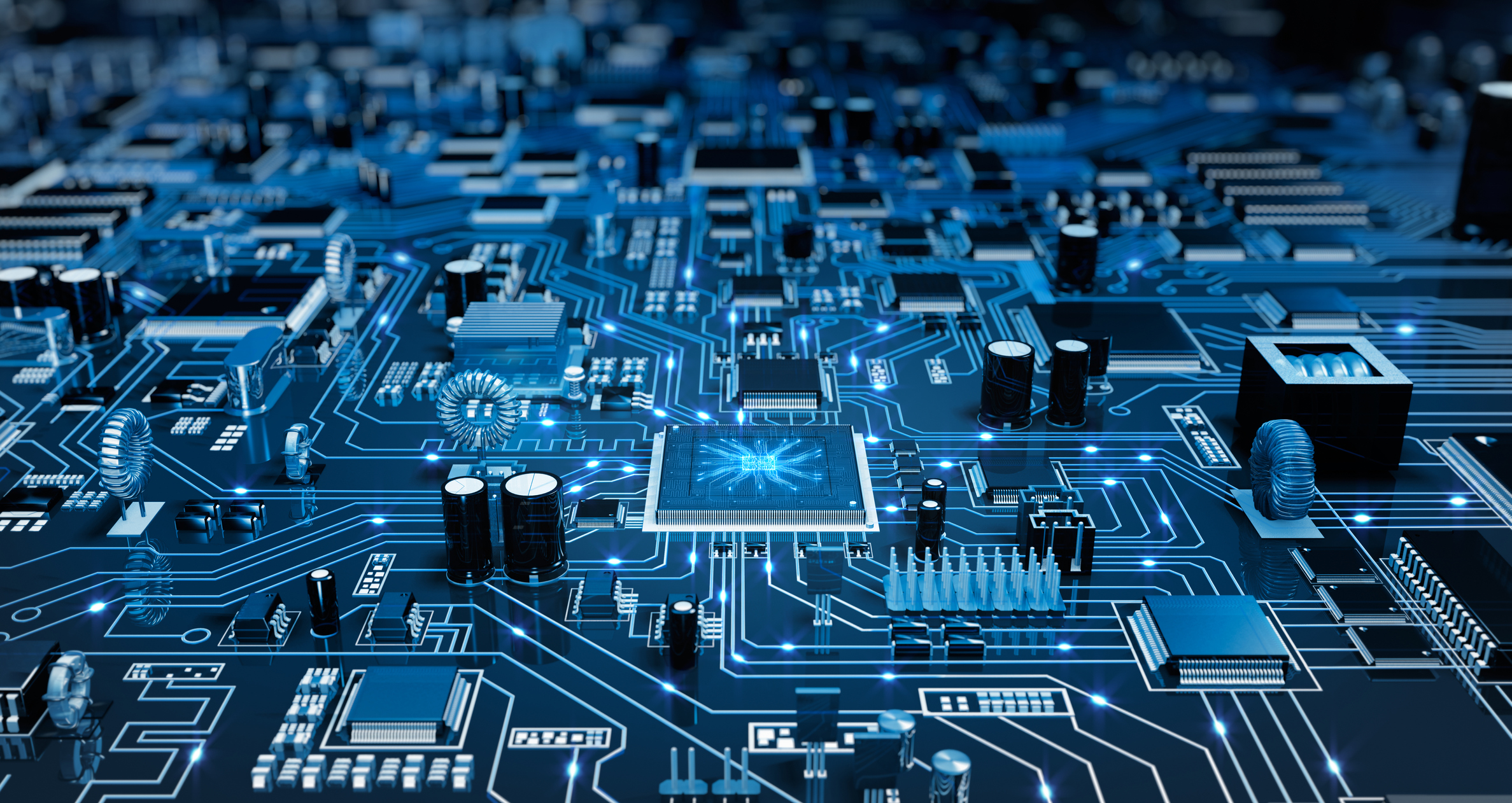新着

430件
-
 10/29 16:18
10/29 16:18【野村の夕解説】日経平均は初の51,000円台 値がさ株の上昇が追い風(10/29)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 29日の日経平均株価は、AI関連銘柄の上昇により大きく反発しました。日経平均株価は寄り付き後急上昇し、51,000円台に達すると、その後は終日、前日比1,000円高を挟んだ水準での推移が続きました。28日の米国株市場での大手テクノロジー株の上昇を受け、日本でも値がさの半導体関連株が上昇し相場をけん引しました。また、28日に約4,000億米ドル規模の「日米間の投資に関する共同ファクトシート」が発表され、AIインフラに関する供給網の強化などに関心を示す日本企業が盛り込まれました。名前が挙がった、ソフトバンクグループ、日立製作所、フジクラなどの企業群は、ビジネス拡大への期待感が高まり株価が上昇し、相場を押し上げました。日経平均株価の終値は前日比1,088円高の51,307円となり、史上最高値を大幅に更新し取引を終えました。個別企業では、アドバンテストが28日に発表した決算内容が好感され、終値でも前日比+22.07%のストップ高まで上昇し、1銘柄で日経平均株価を1,077円押し上げました。一方、東証プライム市場の値下がり数は全体の86%であり、市場全体でみるとやや軟調な展開となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 米国では企業決算がピークを迎え、本日マイクロソフト、アルファベット、メタ・プラットフォームズなど注目のテクノロジー企業の決算発表が行われます。実績に加えてAI関連の設備投資の動向に注目です。 (野村證券投資情報部 清水 奎花) ご投資にあたっての注意点
-
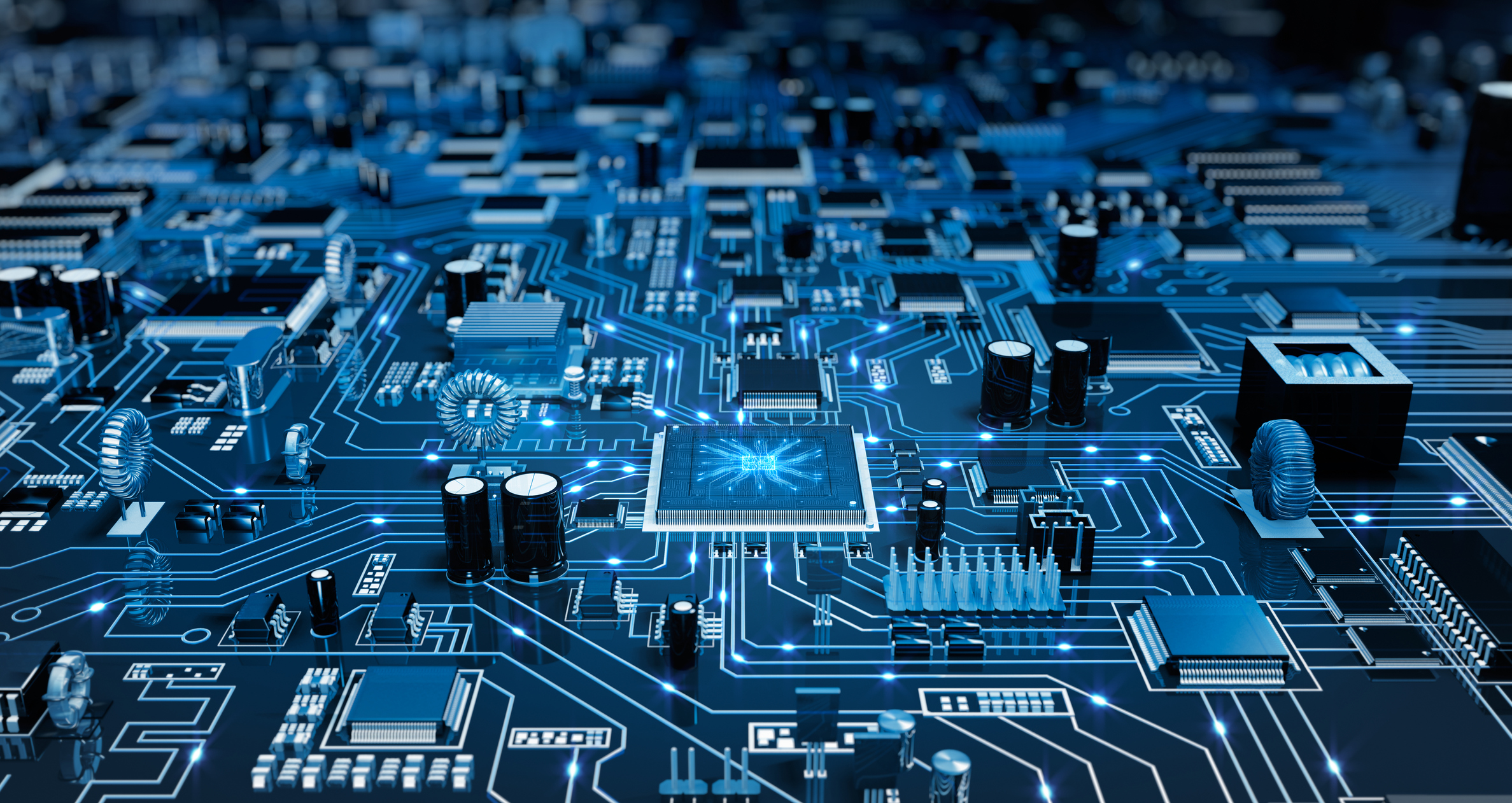 10/29 08:07
10/29 08:07【野村の朝解説】AIによる成長期待がけん引し、米国株上昇(10/29)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 10月29日の米国株式市場では、主要3指数が続伸し、史上最高値を更新しました。トランプ大統領と習近平主席による30日の会談を前に米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことや、29日まで開催される10月FOMCでの追加利下げに対する期待が相場を押し上げました。また、半導体大手エヌビディアによるフィンランドの通信機器大手ノキアとの提携や、米エネルギー省向けに7台のスーパーコンピューターを構築するという報道を受けてエヌビディアの株価が上昇し、相場をけん引しました。さらに、米マイクロソフトと対話型AI「Chat(チャット)GPT」を手掛ける米オープンAIが新規株式公開を視野に入れた組織再編に合意したことでマイクロソフトの株価が上昇し、情報技術セクターの支援材料となりました。 相場の注目点 足元では日米交渉など外交や安保が焦点となっていますが、高市内閣の高い支持率が続けば政策期待が日本株の押し上げ材料となりそうです。また、今週は日米の企業決算発表の序盤戦のピークを迎えます。実績に加えて、会社が示す通期見通しや、情報技術セクターではAI関連の設備投資の動向に注目が集まります。米国では本日のマイクロソフト、アルファベット、メタ・プラットフォームズ、明日のアップル、アマゾン・ドットコム、日本では本日のディスコなど、注目のテクノロジー企業の決算発表が続きます。前日引け後に決算を発表した半導体検査装置のアドバンテストは、AI向け需要の好調を背景に好決算を発表しました。日米株の短期的な過熱感を指摘する声がある中、株価の上昇が本物との見方が強まるためには、AI関連の需要の強さが改めて確認され、好決算が出てくることが必要とみています。また、足元では、日米の金融政策決定会合にも注目です。本日はFOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見が開催されます。本日から明日にかけては日銀金融政策決定会合が開催されます。 (野村證券 投資情報部 坪川 一浩) 注)データは日本時間2025年10月29日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、中心限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ご投資にあたっての注意点
-
 10/28 16:29
10/28 16:29【野村の夕解説】日経平均株価293円安 米財務長官の発言により円高へ(10/28)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は、ベッセント米財務長官による日本の金融政策への言及を受けて円高が進み、軟調に推移しました。寄り付きから、日米首脳会談を控えたリスク回避の動きが見られ、下落して始まりました。会談後は、サプライズがなかったとの見方から一時下げ幅を縮小しました。後場に入ると、27日に開かれた日米財務相会談でベッセント米財務長官が為替について言及し、日本の金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を果たすと発言したと伝わりました。これを受け、市場では日銀の利上げ観測が意識され円高米ドル安が進行し、日経平均株価は再び下落に転じ、最終的に前日比293円安の50,219円で引けました。業種別では、情報・通信業を除く全ての業種が前日比で下落しました。個別では、27日に日本経済新聞社から日経平均株価の構成銘柄から除外されると発表されたニデックが前日比-19.45%のストップ安となり、新規採用のイビデンが同+16.39%の上昇となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 本日米国にて、10月消費者信頼感指数の発表と、29日にかけてFOMCが予定されています。10月のFOMCでは0.25%ポイントの利下げが見込まれており、12月以降の金利動向の見通しについて注目されます。 (野村證券投資情報部 笠原 光) ご投資にあたっての注意点
-
 10/28 09:00
10/28 09:00【週間ランキング】日本株の値上がり/値下がり銘柄は?(10月第4週)
※画像はイメージです。 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(上位) 2025年10月第4週(2025年10月17日~10月24日) 2025年10月月間(2025年9月30日~10月24日) 2025年年間(2024年12月31日~2025年10月24日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2025年10月24日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(下位) 2025年10月第4週(2025年10月17日~10月24日) 2025年10月月間(2025年9月30日~10月24日) 2025年年間(2024年12月31日~2025年10月24日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2025年10月24日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 <参考>今週の日本株式市場パフォーマンス 主要指数 TOPIX: 東証33業種 (注)業種分類は東証33業種ベース。直近値は2025年10月24日時点。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
-
 10/28 08:09
10/28 08:09【野村の朝解説】米中の対立後退でリスクオン一色に(10/28)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 週明け27日の米国株式市場で主要3指数は揃って3営業日続伸し、最高値を更新、S&P500は節目の6,800を突破しました。週末に実施された米中間の貿易協議を受けて、中国によるレアアース輸出規制の1年延期や米国による100%の対中関税発動の見送り方針が報じられ、世界景気の先行き懸念が薄れたことが支えとなりました。加えて、AI市場への本格参入を発表した半導体大手の米クアルコムが一時前日比20%超と急騰し、半導体株を中心に株価上昇したことも指数を押し上げました。一方、安全資産として上昇基調が続いた金(ゴールド)は下落し、VIX指数は約1ヶ月ぶりの水準に低下しました。 相場の注目点 先週は米中両国が強硬姿勢を強めたことで貿易摩擦懸念が再燃しましたが、10月30日の米中首脳会談を前にすでに合意に向けた道筋がみられ、緊張は緩和しています。市場の関心は日米企業の2025年7-9月期決算に移ることが見込まれ、今週は10月29、30日のGAFAM決算が注目されます。日本でも28日のアドバンテストを皮切りに半導体関連企業の決算発表が相次ぎますが、AI需要の強さが改めて確認されれば、日米株式市場のサポート要因になるとみられます。一方、今週は日米欧の中銀会合が集中します。先週公表された9月の米消費者物価(CPI)が市場予想を下回る伸びにとどまり、FRBに対する利下げ観測が維持されているものの、米国株が最高値を更新するなかで、一部では過熱感を指摘する声もきかれます。10月28-29日開催のFOMCでは、今後の利下げ期待が持続するのかどうかが焦点になるとみられます。 本日のイベント トランプ大統領と高市首相が首脳会談を行います。 (野村證券 投資情報部 引網 喬子) 注)データは日本時間2025年10月28日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、中心限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ご投資にあたっての注意点
-
 10/27 15:40
10/27 15:40【野村の夕解説】日経平均株価は史上初の50,000円の大台を突破(10/27)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 27日の日経平均株価は、米中対立の緩和や高市政権に対する期待から、初めて50,000円を突破し、TOPIXとともに史上最高値を更新しました。10月FOMCでの利下げ期待が継続したことや、米中両政府が26日まで実施していた貿易協議で米国が100%の対中関税発動を見送る方向となったことなどを受けて、日経平均株価は寄り付きから大幅に上昇しました。国内の政局面では報道各社の世論調査で高市政権の支持率が軒並み高水準だったことも追い風となり、日経平均株価は50,000円突破後も堅調に推移しました。日経平均株価の寄与度の高いソフトバンクグループやアドバンテストが大幅に上昇したことに加え、28日に行われるトランプ米大統領と高市首相との日米首脳会談で、防衛費や造船分野での協力について話し合う見通しとなったことも材料視され、防衛や造船関連株も軒並み上昇しました。日経平均株価は前営業日比1,212円高の50,512円で取引を終え、東証プライム市場では値上がり銘柄数が全体の約9割を占める全面高となり、東証33業種分類すべてが上昇しました。個別銘柄ではフジクラが同+7.97%、川崎重工業が同+9.02%となり上場来高値を更新しました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 28日には日米首脳会談が行われるほか、国内企業決算発表が序盤戦のピークを迎えます。 (野村證券投資情報部 松田 知紗) ご投資にあたっての注意点
-
 10/27 08:05
10/27 08:05【野村の朝解説】米国株は主要3指数揃って最高値を更新(10/27)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 24日の米国市場では主要3指数が揃って反発し、史上最高値を更新しました。発表が延期されていた9月CPIが市場予想を下回る伸びにとどまったことから、利下げ観測が高まる一方、10月の企業活動を示す総合PMIが予想に反して改善し、今年2番目の高水準となったことを好感したようです。米国債はCPIを好感して買われるもPMI発表後は下落、為替市場では米ドルは対円で一時153円台まで上昇しました。米国債、米ドルの動向に比べて、米国株はやや良いとこ取りの感が強く、過熱感に対する警戒感も根強いようです。 相場の注目点 今週は注目度の高いイベントが目白押しです。金融政策面では28~29日には米国でFOMC、29~30日には日銀の金融政策決定会合、30日にはECBの金融政策理事会が開催されます。市場では、FRBは2会合連続となる0.25%ポイントの利下げが予想される一方、日銀、ECBに関しては金利据え置きの見方が優勢です。 国際政治面では、10月31日~11月1日にAPEC首脳会議が開催されるうえ、28日には日米首脳会談、30日には米中首脳会談が開催される見込みです。日米首脳会談ではロシアからのエネルギー輸入規制の強化、防衛費に拡大などが注目点です。高市首相の外交手腕も注目されます。最も注目度の高い米中首脳会談では、米中関係の緊張緩和につながる話し合いとなるかが注目されます。この点で一定の成果が確認できれば、株式市場にとっては一段の追い風となりそうです。 今週から、米国に続いて日本でも25年7-9月期の決算発表が本格化します。今回の決算シーズンでは、実績だけではなく、2025年度通期の会社見通しの変更が注目されます。 (野村證券 投資情報部 尾畑 秀一) 注)データは日本時間2025年10月27日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、中心限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ご投資にあたっての注意点
-
 10/26 12:00
10/26 12:00【#統合型リゾート(IR)】AI抽出15銘柄/共立メンテ、西武HD、リゾートトラストなど
副首都構想の進展期待、万博跡地再開発とIR計画の注目高まる 自民党は日本維新の会の閣外協力を得て、高市早苗政権を発足させました。維新は「副首都構想」を掲げており、実現すれば大阪の経済が活性化すると期待されています。そうした中、足元では10月13日に閉幕した大阪・関西万博の跡地再開発や統合型リゾート(IR)計画への関心が高まっています。跡地再開発の事業者の公募は2026年春ごろに始まる予定で、世界水準のウォーターパークやサーキット場を整備する案が浮上しています。すでに隣接地では、日本初のカジノを含むIRが2030年の開業を目指して建設工事に着手しています。大阪府は、IR単体で年間2,000万人の来訪者数を見込み、開業後の毎年の経済波及効果は1兆1,400億円に上ると試算しています。AI「xenoBrain」は、「統合型リゾート(IR)開業」が他のシナリオにも波及する可能性を考慮し、影響が及ぶ可能性のある15銘柄を選出しました。 ※ xenoBrain 業績シナリオの読み方 (注1)本分析結果は、株式会社xenodata lab.が開発・運営する経済予測専門のクラウドサービス『xenoBrain』を通じて情報を抽出したものです。『xenoBrain』は業界専門誌や有力な経済紙、公開されている統計データ、有価証券報告書等の開示資料、及び、xenodata lab.のアナリストリサーチをデータソースとして、独自のアルゴリズムを通じて自動で出力された財務データに関する予測結果であり、株価へのインプリケーションや投資判断、推奨を含むものではございません。(注2)『xenoBrain』とは、ニュース、統計データ、信用調査報告書、開示資料等、様々な経済データを独自のAI(自然言語処理、ディープラーニング等)により解析し、企業の業績、業界の動向、株式相場やコモディティ相場など、様々な経済予測を提供する、企業向け分析プラットフォームです。(注3)母集団はTOPIX500採用銘柄。xenoBrainのデータは2025年10月23日時点。(注4)画像はイメージ。(出所)xenoBrainより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
-
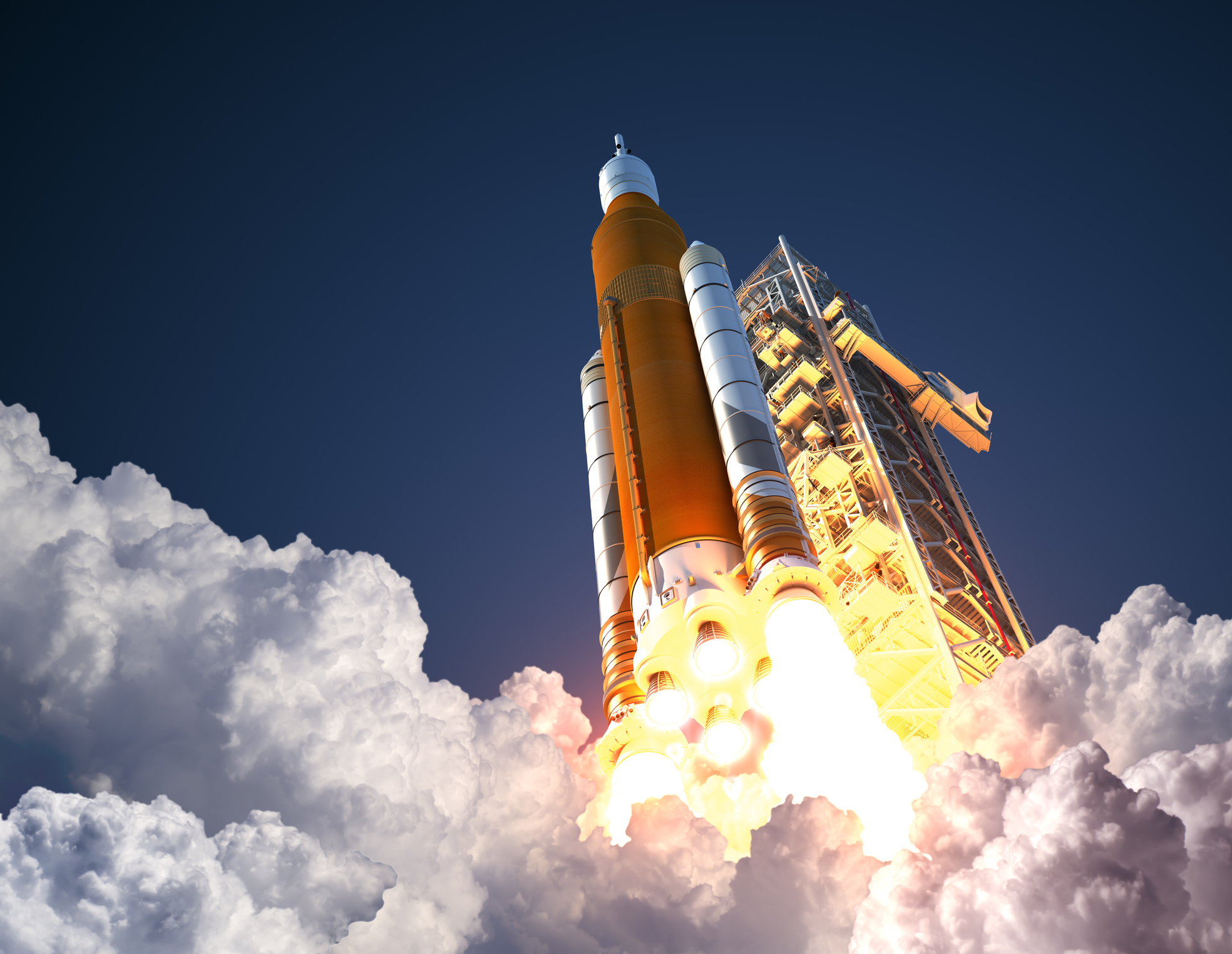 10/26 09:00
10/26 09:00【#ロケット】AI抽出15銘柄/三菱重工、MS&AD、三菱ケミカルなど
世界でロケット開発が加速 JAXAは12月にH3ロケットを打ち上げ 米スペースXは2025年10月13日、大型ロケット「スターシップ」の11回目の試験打ち上げを行い、2回連続の成功となりました。エンジンや燃料タンクを再使用しており、安定運用ができれば、打ち上げ費用が下がり、衛星打ち上げや探査計画の拡充を後押しするとみられます。一方、日本では宇宙航空研究開発機構(JAXA)が10月8日、基幹ロケット「H3」8号機を12月7日に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。新しい衛星の運用が進むことで、位置情報の精度が上がり途切れにくくなります。都市部や山間部でも安定して使えるようになり、災害対応や精密農業、物流の最適化、自動運転・ドローン航行など、位置情報を活用した産業の高度化が進む見通しです。AI「xenoBrain」は、「ロケット需要増加」が他のシナリオにも波及する可能性を考慮し、影響が及ぶ可能性のある15銘柄を選出しました。 ※ xenoBrain 業績シナリオの読み方 (注1)本分析結果は、株式会社xenodata lab.が開発・運営する経済予測専門のクラウドサービス『xenoBrain』を通じて情報を抽出したものです。『xenoBrain』は業界専門誌や有力な経済紙、公開されている統計データ、有価証券報告書等の開示資料、及び、xenodata lab.のアナリストリサーチをデータソースとして、独自のアルゴリズムを通じて自動で出力された財務データに関する予測結果であり、株価へのインプリケーションや投資判断、推奨を含むものではございません。(注2)『xenoBrain』とは、ニュース、統計データ、信用調査報告書、開示資料等、様々な経済データを独自のAI(自然言語処理、ディープラーニング等)により解析し、企業の業績、業界の動向、株式相場やコモディティ相場など、様々な経済予測を提供する、企業向け分析プラットフォームです。(注3)母集団はTOPIX500採用銘柄。xenoBrainのデータは2025年10月15日時点。(注4)画像はイメージ。(出所)xenoBrainより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点

 検索する
検索する