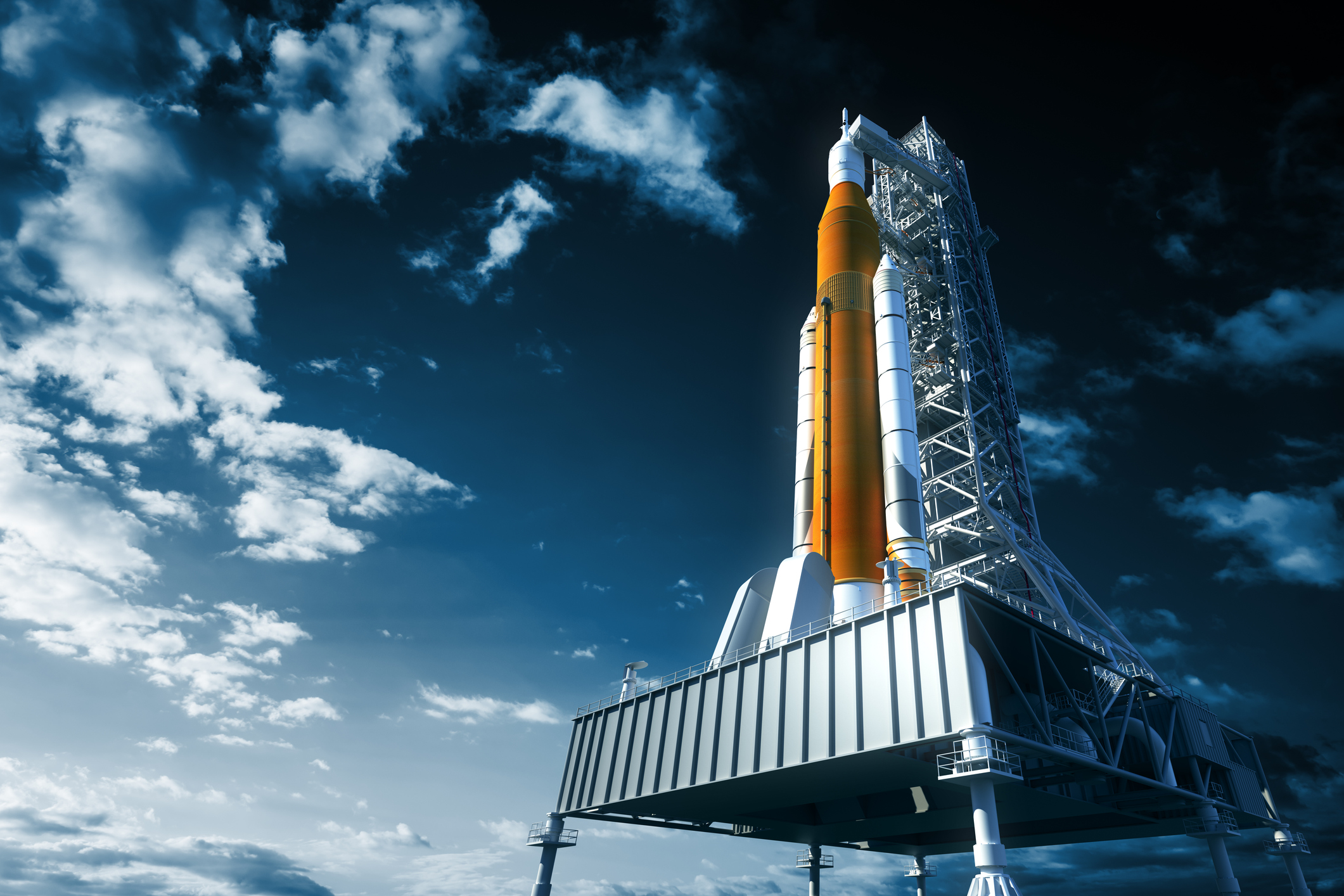-
 56分前
56分前【来週の予定】参院選の結果、株式市場への影響に注目
来週の注目点:参議院議員選挙、主要国の企業景況感 7月20日(日)は、いよいよ参議院議員選挙の投開票日です。足元の報道によれば、自民党と公明党の連立与党が大幅に議席を減らす公算です。野村證券では、連立与党が過半数を維持した場合には25年度の現金給付、過半数割れの場合には25年度の現金給付と26年度の消費税減税が実施されると見ています。これらは一時的な景気押し上げ効果が期待できる一方、基調的な経済成長率及び物価上昇率を押し上げる効果は期待しにくいでしょう。仮に連立与党が大幅な過半数割れとなった場合には、政策の不透明感が高まり、株式市場が不安定となる可能性があります。また、拡張的な財政が継続するとの見方が強まった場合には、長期金利が一段と上昇するリスクには注意が必要です。 日本の経済指標は24日(木)に7月S&Pグローバル日本PMI速報値が発表されます。トランプ関税の影響が懸念されます。また、25日(金)に7月東京都区部消費者物価指数が発表されます。コアCPIは前年同月比+2.9%と、前月の同+3.1%から減速すると野村證券では予想します。米価格の下落に伴う食料価格の上昇一服が一因です。 米国では、7月29日(火)~30日(水)のFOMCを控え、 FRBは19日(土)から金融政策に関する発言を控えるブラックアウト期間に入ります。そのため、市場の注目は足元の経済指標に移ると見られます。23日(水)に6月中古住宅販売件数、24日(木)に7月S&Pグローバル米国PMI速報値、6月新築住宅販売件数、25日(金)に6月耐久財受注などの経済指標が発表されます。 ユーロ圏では、24日(木)にECBが金融政策理事会を開催します。今会合では政策金利が据え置かれ、9月、12月に追加利下げを実施すると野村證券では予想します。また、24日(木)にユーロ圏及びドイツの7月HCOB PMI速報値、25日(金)にドイツの7月Ifo企業景況感指数が発表されます。積極的な財政政策への転換や、ECBによるこれまでの利下げが景況感を押し上げると見ています。 (野村證券投資情報部 坪川 一浩) (注1)イベントは全てを網羅しているわけではない。◆は政治・政策関連、□は経済指標、●はその他イベント(カッコ内は日本時間)。休場・短縮取引は主要な取引所のみ掲載。各種イベントおよび経済指標の市場予想(ブルームバーグ集計に基づく中央値)は2025年7月18日時点の情報に基づくものであり、今後変更される可能性もあるためご留意ください。(注2)画像はイメージです。(出所)各種資料・報道、ブルームバーグ等より野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
-
 昨日 16:17
昨日 16:17【野村の夕解説】日経平均82円安 参議院議員選挙を前に上値重く(7/18)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 18日の日経平均株価は、20日に行われる参議院議員選挙の投開票を控えて、上値の重い展開となりました。17日の米国株高の流れを引き継ぎ、日経平均株価は寄り付き前日比171円高の40,072円と、取引時間中としては7月4日以来2週間ぶりに4万円台を回復する場面もありました。しかし、7月に入って以降、上昇が続いていた値がさ株のアドバンテストや、前日引け後の決算発表を受けて、業績の先行き悪化への懸念が強まったディスコの株価急落が下押し圧力となり、日経平均株価は下落に転じました。最先端AI技術の導入でみずほフィナンシャルグループと提携を交わしたソフトバンクグループが1銘柄で日経平均株価を108円押し上げる上昇をみせたものの、参議院議員選挙を前に市場の様子見姿勢が広がる中、日経平均株価の戻りは鈍く、終値は前日比82円安の39,819円となりました。アドバンテストは前日比-4.44%、ディスコは同-8.79%となり、2銘柄で日経平均株価を168円押し下げました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 20日は参議院議員選挙の投開票日です。各種観測報道にあるように与党過半数割れとなった場合、財政悪化や日米関税交渉進展の遅れに対する懸念が強まり、株式市場の変動が大きくなる可能性があることから、注意が必要です。 (野村證券投資情報部 秋山 渉) ご投資にあたっての注意点
-
 昨日 12:00
昨日 12:00【今週のチャート分析】6月下旬の変化で見えた、日経平均中長期上昇シナリオ
※画像はイメージです。 ※2025年7月17日(木)引け後の情報に基づき作成しています。 25日移動平均線を下支えとして再度4万円台へ 今週の日経平均株価は、円安進行が好感された一方、週末の参議院議員選挙や米関税政策に対する警戒感などから、上値は限定的でした。 チャート(図1)でこれまでの動きを見ると、6月下旬に5月以降の中段保ち合いを上放れし、年初来高値(6月30日、ザラバベース:40,852円)をつけました。その後は押しが入りましたが、これまで下支えとなってきた25日移動平均線(7月17日:39,325円)が今回も下支えとなっており、今後も同様の動きが続くか注目されます。仮に同線を割り込んだ場合は200日線(同:38,151円)が次の下値メドとして挙げられます。 (注1)直近値は2025年7月17日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 一方、週足チャート上(図2)では、6月下旬の大幅上昇により、52週移動平均線(7月17日:38,031円)と昨年7月高値以降の下降トレンドライン(6月中旬:38,300円前後)を明確に上抜けました。これにより中長期上昇トレンド入りの可能性が高まっています。この先4万円台を回復となれば、年初来高値(6月30日:40,852円)更新を目指す動きが期待されます。 (注1)直近値は2025年7月17日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 夏枯れを越えて高値更新なるか、2027年には5万円台への試算値も 日経平均株価は6月末に4万800円台を付けたものの、その後は上値の重い展開が続いています。今回は4月以降の動きを振り返り、中長期的な視点で今後の見通しを考えてみましょう(図2・図3)。 日経平均は今年4月の安値形成後に急速に上昇しましたが、52週移動平均線付近で一時的に戻り待ちの売りが優勢となりました。この52週線は1年間の週末終値の平均で、実質的に年間のコストとして意識されやすいためです(図2)。 しかし、6月下旬には中東情勢の緊張緩和や米ハイテク株の上昇を背景に、下降トレンドラインと52週線を明確に上抜けました。これにより、今年4月安値付近まで再度下落するリスクが低下し、中長期の上昇トレンドに入った可能性が高まっています。 7月に入って一時調整していますが、夏枯れ相場となっても52週線が下支えとなる動きが期待されます。調整後の上昇が続けば、まずは昨年7月の史上最高値更新が注目されます。前回の中長期上昇局面(22/3~24/7)の上昇倍率(1.7倍)や上昇期間(約2年)を今年4月安値に当てはめて試算すると、2027年には5万円台の達成も視野に入っています(図3)。 (注1)直近値は2025年7月17日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(注3)日柄は両端を含む。(出所)日本経済新聞社、各種資料より野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 岩本 竜太郎) ご投資にあたっての注意点
-
 56分前
56分前【来週の予定】参院選の結果、株式市場への影響に注目
来週の注目点:参議院議員選挙、主要国の企業景況感 7月20日(日)は、いよいよ参議院議員選挙の投開票日です。足元の報道によれば、自民党と公明党の連立与党が大幅に議席を減らす公算です。野村證券では、連立与党が過半数を維持した場合には25年度の現金給付、過半数割れの場合には25年度の現金給付と26年度の消費税減税が実施されると見ています。これらは一時的な景気押し上げ効果が期待できる一方、基調的な経済成長率及び物価上昇率を押し上げる効果は期待しにくいでしょう。仮に連立与党が大幅な過半数割れとなった場合には、政策の不透明感が高まり、株式市場が不安定となる可能性があります。また、拡張的な財政が継続するとの見方が強まった場合には、長期金利が一段と上昇するリスクには注意が必要です。 日本の経済指標は24日(木)に7月S&Pグローバル日本PMI速報値が発表されます。トランプ関税の影響が懸念されます。また、25日(金)に7月東京都区部消費者物価指数が発表されます。コアCPIは前年同月比+2.9%と、前月の同+3.1%から減速すると野村證券では予想します。米価格の下落に伴う食料価格の上昇一服が一因です。 米国では、7月29日(火)~30日(水)のFOMCを控え、 FRBは19日(土)から金融政策に関する発言を控えるブラックアウト期間に入ります。そのため、市場の注目は足元の経済指標に移ると見られます。23日(水)に6月中古住宅販売件数、24日(木)に7月S&Pグローバル米国PMI速報値、6月新築住宅販売件数、25日(金)に6月耐久財受注などの経済指標が発表されます。 ユーロ圏では、24日(木)にECBが金融政策理事会を開催します。今会合では政策金利が据え置かれ、9月、12月に追加利下げを実施すると野村證券では予想します。また、24日(木)にユーロ圏及びドイツの7月HCOB PMI速報値、25日(金)にドイツの7月Ifo企業景況感指数が発表されます。積極的な財政政策への転換や、ECBによるこれまでの利下げが景況感を押し上げると見ています。 (野村證券投資情報部 坪川 一浩) (注1)イベントは全てを網羅しているわけではない。◆は政治・政策関連、□は経済指標、●はその他イベント(カッコ内は日本時間)。休場・短縮取引は主要な取引所のみ掲載。各種イベントおよび経済指標の市場予想(ブルームバーグ集計に基づく中央値)は2025年7月18日時点の情報に基づくものであり、今後変更される可能性もあるためご留意ください。(注2)画像はイメージです。(出所)各種資料・報道、ブルームバーグ等より野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
-
 昨日 16:17
昨日 16:17【野村の夕解説】日経平均82円安 参議院議員選挙を前に上値重く(7/18)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 18日の日経平均株価は、20日に行われる参議院議員選挙の投開票を控えて、上値の重い展開となりました。17日の米国株高の流れを引き継ぎ、日経平均株価は寄り付き前日比171円高の40,072円と、取引時間中としては7月4日以来2週間ぶりに4万円台を回復する場面もありました。しかし、7月に入って以降、上昇が続いていた値がさ株のアドバンテストや、前日引け後の決算発表を受けて、業績の先行き悪化への懸念が強まったディスコの株価急落が下押し圧力となり、日経平均株価は下落に転じました。最先端AI技術の導入でみずほフィナンシャルグループと提携を交わしたソフトバンクグループが1銘柄で日経平均株価を108円押し上げる上昇をみせたものの、参議院議員選挙を前に市場の様子見姿勢が広がる中、日経平均株価の戻りは鈍く、終値は前日比82円安の39,819円となりました。アドバンテストは前日比-4.44%、ディスコは同-8.79%となり、2銘柄で日経平均株価を168円押し下げました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時45分頃。米ドル/円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。米ドル/円は11:30~12:30の間は表示していない。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 20日は参議院議員選挙の投開票日です。各種観測報道にあるように与党過半数割れとなった場合、財政悪化や日米関税交渉進展の遅れに対する懸念が強まり、株式市場の変動が大きくなる可能性があることから、注意が必要です。 (野村證券投資情報部 秋山 渉) ご投資にあたっての注意点
-
 昨日 12:00
昨日 12:00【今週のチャート分析】6月下旬の変化で見えた、日経平均中長期上昇シナリオ
※画像はイメージです。 ※2025年7月17日(木)引け後の情報に基づき作成しています。 25日移動平均線を下支えとして再度4万円台へ 今週の日経平均株価は、円安進行が好感された一方、週末の参議院議員選挙や米関税政策に対する警戒感などから、上値は限定的でした。 チャート(図1)でこれまでの動きを見ると、6月下旬に5月以降の中段保ち合いを上放れし、年初来高値(6月30日、ザラバベース:40,852円)をつけました。その後は押しが入りましたが、これまで下支えとなってきた25日移動平均線(7月17日:39,325円)が今回も下支えとなっており、今後も同様の動きが続くか注目されます。仮に同線を割り込んだ場合は200日線(同:38,151円)が次の下値メドとして挙げられます。 (注1)直近値は2025年7月17日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 一方、週足チャート上(図2)では、6月下旬の大幅上昇により、52週移動平均線(7月17日:38,031円)と昨年7月高値以降の下降トレンドライン(6月中旬:38,300円前後)を明確に上抜けました。これにより中長期上昇トレンド入りの可能性が高まっています。この先4万円台を回復となれば、年初来高値(6月30日:40,852円)更新を目指す動きが期待されます。 (注1)直近値は2025年7月17日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 夏枯れを越えて高値更新なるか、2027年には5万円台への試算値も 日経平均株価は6月末に4万800円台を付けたものの、その後は上値の重い展開が続いています。今回は4月以降の動きを振り返り、中長期的な視点で今後の見通しを考えてみましょう(図2・図3)。 日経平均は今年4月の安値形成後に急速に上昇しましたが、52週移動平均線付近で一時的に戻り待ちの売りが優勢となりました。この52週線は1年間の週末終値の平均で、実質的に年間のコストとして意識されやすいためです(図2)。 しかし、6月下旬には中東情勢の緊張緩和や米ハイテク株の上昇を背景に、下降トレンドラインと52週線を明確に上抜けました。これにより、今年4月安値付近まで再度下落するリスクが低下し、中長期の上昇トレンドに入った可能性が高まっています。 7月に入って一時調整していますが、夏枯れ相場となっても52週線が下支えとなる動きが期待されます。調整後の上昇が続けば、まずは昨年7月の史上最高値更新が注目されます。前回の中長期上昇局面(22/3~24/7)の上昇倍率(1.7倍)や上昇期間(約2年)を今年4月安値に当てはめて試算すると、2027年には5万円台の達成も視野に入っています(図3)。 (注1)直近値は2025年7月17日時点。(注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(注3)日柄は両端を含む。(出所)日本経済新聞社、各種資料より野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 岩本 竜太郎) ご投資にあたっての注意点

 検索する
検索する